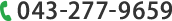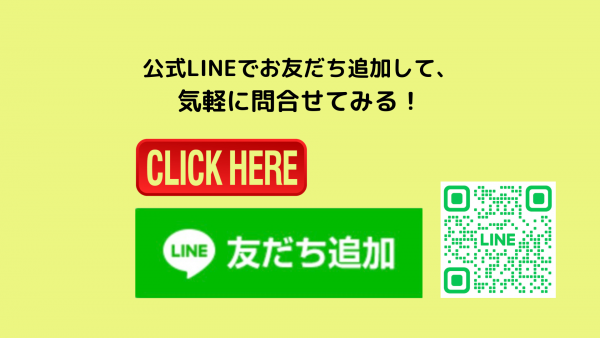今回の、コラムでは弊社にアパレルoem生産依頼が多いアイテムの一つであるTシャツに使われているテキスタイル(生地)について、どう作られているかを解説したいと思います。
Tシャツと言ってもいろいろな種類がありますが、今回は綿の一般的なカジュアルTシャツについて、そのテキスタイル(生地)になるまでの工程として、糸を作る紡績・その糸を生地にする製編(編立)・その生地を染める染色の順で解説したいと思います。
目次
紡績
製編(編立)
染色
まとめ
紡績
紡績は、綿花を一定方向に揃え撚りをかけ1本の糸にする工程です。綿花の産地としてはアメリカ・インド・オーストラリア・中国・パキスタンなどがあります。そこで採取された綿花を紡績工場で糸にする工程としては、開俵→混打綿→梳綿(カード)・コーマー工程→練条→粗紡→精紡→仕上げという流れです。
🔴🔴関連記事、「綿(Cotton)素材について」はこちらをクリック、
👇👇👇👇👇

開俵・混打綿

入荷した原料の綿(1俵200kgぐらい)のワタを開俵しリラックスさせます。糸の品質が生産時期によって変わらないように数種類のワタを混ぜながら、よりリラックスさせる工程を混打綿といい、この段階で、ワタに入っている大きめの夾雑物(ゴミなど)を取り除きます。
梳綿(カード)・コーマー

綿のワタを糸にしやすくするため一方方向へ揃えていきます。この工程でも、短いワタや夾雑物を除去し、ワタを太い(直径2〜3cm)紐状にします。これをスライバーといいます。
この工程のあと、高級な綿糸を作る場合は、コーマー工程(櫛のようなものでワタを揃える工程)で繊維長の短いワタを除去します。コーマー工程を通したいとは、糸がより均一で光沢がありソフトな風合いです。
練条

前工程(梳綿(カード)・コーマー工程)でできたスラーバーをワタのロット差や日によるロット差がでないように何本も繰り返し合わせて混ぜていきます。綿とポリエステル、綿とレーヨンを混ぜるような糸(混紡糸)は、この工程でポリエステルのスライバー、レーヨンのスライバーと混ぜていきます。
粗紡

粗紡工程では、練条で出来上がったスライバーをここでも混ぜ合わせ最終的には紡績機械に供給できる形状にします。この形状を粗糸といい、若干、ワタが素抜けしないように撚りが掛かっています。
精紡

上の写真が一般的な精紡機でリング精紡機と言われています。上にかかっているものが前工程で作られた粗糸で、オレンジの色の部分のローラーで引き伸ばし撚りが掛かり下の部分(ボビン)で巻き取っていきます。1日の生産量はこのボビンを巻き取る数(錘数・スイスウと読みます)で表し、日本の紡績工場のピークの錘数は1100万錘でしたが、現在は100万錘を優に切っているので10分の1の生産量まで減少し中国・ASEANなどに生産移行たということになります。

この精紡機は、リング精紡機とは違うタイプのOE(オープン・エンド)精紡機です。特徴としては粗紡工程が省略できスライバーを直精紡機に供給し糸にするということとボビンに巻き取っていないので(写真上側)このまま生地にする事ができる、省力化・量産化が可能な精紡機です。
しかし、このOE精紡機のデメリットとしては細い番手の糸ができないということと、これはメリットにもなりますが糸に自然なムラがある・風合いにシャリ感があるということです。
仕上げ

仕上げ工程は、紡績された糸を出荷できる形状に巻き取る工程です。巻き取ると同時に糸のムラ部分や、夾雑物(ゴミなど)を除去します。欠点をカットしたときや新しいボビンの糸地のつなぎ目は、あと工程の製織(生地を織る)・製編(生地を編む)時に生地品質のトラブルにならないように結び目を小さくしたり、空気の力で繋いだりしています。
ここまでが紡績工程です。ただ糸を作るにも多くの工程があることが分かって頂けたと思います。
製編(編立)

Tシャツには、本体部分と襟部分の2種類の生地が使われており、上の写真のような丸編機で生地を編みます。本体部分の生地は一般的には天竺編み、襟部分はフライス編み(リブ編み)で、この2種類の生地は同じ編み機では編めないため2種類の機械(編機)を使う必要があります。
写真の側面にあるクリールというところに糸(写真の白いもの)を置き、パイプの中を通って機械に糸を供給し、中心部のところにある数千本の編み針で生地を編んでいき、針の動き方によって色々な組織の生地を編むことができます。シャツなどに使う織物は経糸を用意する必要がありますが丸編みニットはその必要がないとことが大きな特徴で編機を稼働させた瞬間から生地ができあがり、生地(生機・染色前の生地でキバタと読みます)はチューブ状で上がってきますので丸編機といいます。
おおよそ、8時間でTシャツ用の生地なら400枚ぐらいの量の生地を編むことができます。
【編立の動画】
染色

次の工程は、編立された生機に色を付ける染色工程です。一般的なTシャツの生地は、綿なので一般的には反応性染料を使用し色を付けていきます。写真のような染色機で、精錬・漂白(生機の汚れ、夾雑物をとり染料が付きやすい状態にする)→染色を行います。シロや薄いピンクなど淡色で、染色時間は4時間ぐらい、黒などの濃色で8時間ぐらいの染色時間がかかります。
染色機は、サンプルを染める10kg染色機から量産する1000kg染色機までさまざまな大きさの染色機があります。サンプルを染める10kgでもTシャツでいうと40〜50枚ぐらいの量になります。
【染色の動画】

染色機で染色した生地は、円錐脱水機で脱水後、上の写真の様なテンターという乾燥機で生地が縮まないようにセットしたり、抗菌防臭加工などの機能加工薬剤を付けたりします。
このテンターが終わったら汚れ・穴傷等欠点を検反し縫製工場へ出荷します。
まとめ
以上が、一般的なTシャツに使うテキスタイル(生地)の作り方(作る工程)です。
海外の繊維工場は、紡績・編立・染色、または編立・染色を一つの会社で行いますが、日本の多くの場合は、紡績・編立・染色は別々の会社が行う分業の場合が多いのが業界の特徴です。この様な特徴から人件費の差にも加えスピード感(納期)や、コスト感の違いがでているかもしれません。
また、テキスタイル(生地)を作るだけで、このような多くの工程が存在するのも、少ロット化・スピード化が難しい要素になっているかもしれません。
【作成事例】
最後に、セールストークになって申し訳ありませんが、弊社の特徴は、この全ての工程に経験・精通し物作りができることで、お客様のご希望の多い少ロットにも可能な限り対応できることなです。という事なのでアパレルoemに関する、色々なお問い合わせをお待ちしております。
この度は、最後までコラムを読んで頂きありがとうございました🙏‼
今後も、引き続きアパレル・繊維業界の色々な情報をコラムアップしていきますので、よろしくお願いします‼
🔴以下の弊社HP・公式LINE・instagramでも情報公開・お問合せの対応などもしておりますので、
お気軽にアクセスお願いします。
お問い合わせ